2023年12月7日
一般質問② オンラインを活用した遠隔医療について
〈地域医療デジタル改革加速化事業〉
-
高画質モバイル中継装置の導入支援
離島等へき地を有する市町等に対し、巡回診療等で活用可能な高画質モバイル中継装置の整備を支援
-
活用事例の共有に向けたセミナーや見学会等の開催
課題の共有や展開方法についての意見交換、セミナー
機器の導入済の施設の協力を得て、実証現場の見学会(Web会議を含む)
この度の実証事業の成果と、これらの取組を踏まえたオンラインを活用した遠隔医療の更なる充実について、県としてどのようにお考えか、見解を伺います。
健康福祉部長の答弁
県では、離島などのへき地において、持ち運び可能な中継装置を使用し、離島等に滞在する看護師からへき地医療拠点病院の医師に、高解像度の映像を送り、皮膚の状況や傷口の回復状況を診察するなど、遠隔医療の実証に取り組んだところです。
その成果として、5G環境と同様に高画質で遅延なく動画を送ることが確認されたことから、へき地においても、技術面においては対面診療と遜色ない診療が可能であることが実証できたと考えています。
実証に協力いただいた患者からは「オンラインでも医師と会話でき、安心して診療を受けることができた」との声もいただいており、また、拠点病院の医師からも「手術を受けた患者が退院して離島に戻った後も、継続して経過観察ができる」など、一定の評価を得たところです。
こうした成果を踏まえ、遠隔医療の社会実装に移行したところであり、市町や医療機関に対し、有効性を周知するとともに、導入経費が高額であるなどの課題もあることから、県としては、通信機器等の導入支援を行うなど、へき地における遠隔医療の普及促進を図っているところです。
令和5年11月定例会 会議録より
◆福田吏江子
オンラインを活用した遠隔医療のさらなる充実について質問いたします。
本県では、令和4年度に地域医療デジタル改革加速化事業を実施しており、5G環境での遠隔医療支援体制の構築と併せ、離島などの多様な現場で新たなデジタル技術を活用することで、遠隔医療の加速化を図り、医療提供体制の充実を目指すことを趣旨として、5G環境での遠隔医療支援の実証と併せて、離島で巡回診療している医療機関へ高画質モバイル中継装置を貸し出す実証事業を展開してきました。
このたびは、この高画質モバイル中継装置での実証事業の成果を踏まえた、さらなる活用についてお伺いいたします。
本事業で導入された高画質モバイル中継装置は、小さな通信装置で持ち運びができる大きさのため、大がかりな整備が必要なく、装置を移動させることができることから、県内のほかの場所でも活用できるとのこと。また、4Gという従来の通信ではありますが、複数回線に分散してデータを伝送するマルチリンクとすることで、大容量は送れなくとも、通信速度は5Gと遜色なく、普通の画面よりクリアに映し出され、皮膚の色なども目の前にあるときと変わらないくらいであったということは、この装置の大きなメリットであったのだと理解しております。
離島などの常駐している医師が少ない診療所において、悪天候で医師が診療所に行くことができないときも対面と同じように診療ができるかということは、限られた医療資源の中でも医療提供体制の充実へとつながると考えます。
そこで、本事業を通して、どのような成果を得られ、また地域の皆様からはどのようなお声が届いているでしょうか。また、本事業から見えてきた課題はどのようなものでしょうか、お伺いいたします。
また、オンライン診療については、現在、国の社会保障審議会医療部会で様々議論がなされており、規制改革推進会議、健康・医療・介護ワーキング・グループの基本認識として、オンライン診療の普及・促進は患者本位の医療サービスの提供を実現するためである、持病を抱えながらデイサービスを利用されている歩行困難なお年寄りの方、ひきこもりの方、都市にお住まいでもご家族の育児・介護がある中通院の同伴で仕事を休まないといけない方、地域によっては近くに医療機関がない方など、オンライン診療を必要とされる様々な方がいらっしゃる。オンライン診療は利用者起点の徹底の観点から、患者と医師が現場でオンラインか対面かを柔軟に選択できる制度整備の検討が求められるという意見が報告されております。
私は、僻地や準僻地に限らず、オンライン診療によって、自宅にいても診療してもらえる可能性が広がることで、特に、外出が難しく待合室で長時間待機することがつらいお子さん連れの方にも対面診療の回数の軽減による移動の負担減も図れるのではないかと考えます。
このたびの実証事業の成果とこれらの取組を踏まえたオンラインを活用した遠隔医療のさらなる充実について、県としてどのようにお考えでしょうか、ご見解をお伺いいたします。
◎健康福祉部長
オンラインを活用した遠隔医療のさらなる充実についての2点のお尋ねにお答えします。
医療資源が限られた地域においても、必要な医療が提供できる体制の確保・充実を図ることが重要であることから、県では、保健医療計画に基づき、離島などの僻地においても十分な医療が提供できるよう、オンラインを活用した遠隔医療の普及促進に努めているところです。
まず、高画質モバイル中継装置を活用した実証事業における成果や課題等についてです。
県では、離島などの僻地において、持ち運び可能な中継装置を使用し、離島等に滞在する看護師から僻地医療拠点病院の医師に、高解像度の映像を送り、皮膚の状況や傷口の回復状況を診察するなど、遠隔医療の実証に取り組んだところです。
その成果として、5G環境と同様に高画質で遅延なく動画を送ることが確認されたことから、僻地においても、技術面では対面医療と遜色ない診療が可能であることが実証できたと考えています。
実証に協力いただいた患者からは、オンラインでも医師と会話でき安心して診療を受けることができたとの声も頂いており、また、拠点病院の医師からも、手術を受けた患者が退院して離島に戻った後も、継続して経過観察ができるなど、一定の評価を得たところです。
こうした成果を踏まえ、遠隔医療の社会実装に移行したところであり、市町や医療機関に対し、有効性を周知するとともに、導入経費が高額であるなどの課題もあることから、県としては、通信機器等の導入支援を行うなど、僻地における遠隔医療の普及促進を図っているところです。
次に、オンラインを活用した遠隔医療のさらなる充実についてです。
厚生労働省が本年6月に策定した、オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針では、オンライン診療は、患者の継続治療や医師の負担軽減の観点から有用である一方で、対面診療が基本であることから、両者を適切に組み合わせて行うよう示されています。
県としては、まずは医療資源が特に限られた離島などの僻地において、オンラインを活用した遠隔医療の普及促進を図るとともに、国の動向を把握しながら、引き続き関係市町や医療機関と連携・協力して、地域医療提供体制の充実に努めてまいります。



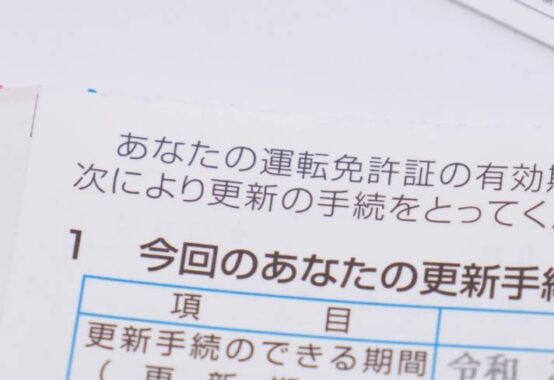







この記事へのコメントはありません。